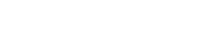京都に住んでいる他国人のせいか、京都のことが気になります。最近、ある新聞のコラムで京都の「ハレ」と「ケ」という言葉を知りました。ハレは非日常、ケは日常。その両者を区別しながらも断絶させず、連続性と非連続性を大切にしてきた京都の文化が、観光促進の掛け声におされて最近うすれつつある、というような辛口のエッセイでした。
そのハレとケからふと想ったのは、京都の文化ならず、信仰の世界でした。ハレはさだめし典礼、ケは日々の祈り、との想い。日々の祈りという地下水のようなケがなければハレという典礼は生きてはこず、典礼という非日常がケに活力を与えて持続を可能にする、ちょっと手前みそかなとは思いながらも、まったく異質なふたつの文化が深いところでつながっている、そんな感じがしたものです。

前回ご紹介したアビラのテレサの言葉は、ケとしての日々の祈りを十分に表現しています。ところで、そのなかにある「ふたりだけで友情を交わし合う」というテレサの言葉に、みなさんはどのような印象をもたれたでしょうか。さっと読みとばせば何の変哲もない表現ですが、実は、わたしたちの神との関わりのなかでとても重要なことが含まれています。いったい神様との友情などということがあり得るのでしょうか。
現代には言葉としての「愛」、「やさしさ」、「友情」は溢れています。「○○にやさしい」ことが商品のセールスポイントとなり、歌の歌詞に愛や恋愛、そして友情がもられていないものはほとんどありません。しかしその一方で、多発する子供たちの陰湿ないじめや、不条理な殺人、自殺の増加といった社会の病理的な現象は、まさにそれらの言葉が実体をもっていないことを表わしています。わたしたち人間が相互に手をのばしあって求めようとあがき、なおかつ手に入れることの難しい愛や友情、それをテレサはイエス様との関わりのなかにしっかりと手にしているように見えるのです。
では友情とは何なのでしょう。
あらゆる種類の愛(と見えるもの)が友情であるわけではありません。友情には二つの特徴がある、とキリスト教の著名な神学者が語っています。ひとつは、相手の幸福を願うこと、そしてもうひとつ重要なことは、双方の分かち合い、お互いに自分のもっとも大切なものを与えあうことです。相手への好意や、幸福を思う心だけでは十分ではなく、それが相互に行われなければなりません。すると、友情には双方が同じ地平にたっていること、対等であることが求められるのがわかります。上から目線や、強いものに依存する恐れの目線のなかに友情はありません。友情の反対は、相手を支配したいという欲望であり、自分のために相手を利用したいという打算です。
この友情をイエス様はわたしたちに差し出しておられます。当時の支配階級である宗教家から、宗教の名のもとに社会の底辺に追いやられた人々にいたるまで、あらゆる人々と対等に関わられたイエス様を通して、神様はわたしたちと同じ目線にまで降られた、それは福音書が現代のわたしたちに伝えようとしている重要なメッセージのひとつです。言葉を換えれば、イエス様はご自分と共に生きようとする人々を、ご自分のところまで引き上げてくださる、友としてくださる、ということなのです。
「もはや、わたしはあなたがたを僕とは呼ばない。僕は主人が何をしているか知らないからである。わたしはあなたがたを友と呼ぶ。」(ヨハネ15・15)
このように友としてわたしたちの人生に寄り添おうとされるイエス様に、どうすればこたえられるかともし自問するなら、それはキリスト者として生きていく決断のときかもしれません。わたしの生き方をイエス様の生き方に重ねながら、友情を深める手段としての祈りを続けます。「友情の親密な交換」としての祈り、まさに「ケ」の世界です。そこには何ら人目を引く華々しさはありません。毎日の平凡な営み、人々とのときに苦労の多い関わり、それら生きていくための地道な日々のなかに、地下水のように祈りというケが浸みとおっていきます。その祈りをとおし、イエス様との友情をとおしてわたしたちは少しずつ、ほんの少しずつイエス様にふさわしいものとされていきます。
アビラのテレサはイエス様との友情を深く生きていました。彼女にとって祈りは自分の生き方を支えるなくてはならないものでした。そして彼女の生き方とは、まさにイエス様の生き方そのもの、イエス様のように人々を愛すること(ヨハネ13・34)でした。祈りはキリスト者の生き方に深く結ばれています。
つづく
文:中山真里